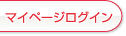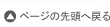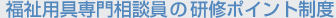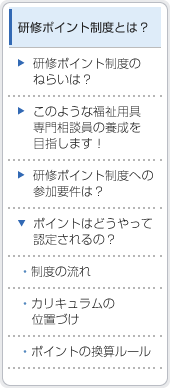
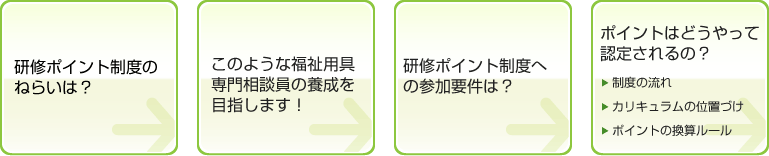

利用者のニーズの変化(認知症への対応等)や地域包括ケアの推進といった流れを受け、介護保険制度における福祉用具サービスのさらなる質の向上が、強く求められています。そのためには、福祉用具専門相談員の資質の向上が鍵となります。
福祉用具専門相談員は、業務や研修等を通じて実践力を磨いていますが、それを証明するのは困難なのが現状です。利用者や介護支援専門員に質の高いサービスを選択していただける環境を整備していくためには、福祉用具専門相談員の持つ専門性と、その習得過程を知ってもらうことが有効だと考えています。
福祉用具専門相談員にとっても、スキルの習得過程と、キャリア形成の関係が明確になることで、スキルアップへの動機がより高まると考えています。
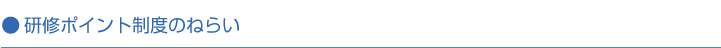
福祉用具専門相談員は、業務や研修等を通じて実践力を磨いていますが、それを証明するのは困難なのが現状です。利用者や介護支援専門員に質の高いサービスを選択していただける環境を整備していくためには、福祉用具専門相談員の持つ専門性と、その習得過程を知ってもらうことが有効だと考えています。
福祉用具専門相談員にとっても、スキルの習得過程と、キャリア形成の関係が明確になることで、スキルアップへの動機がより高まると考えています。
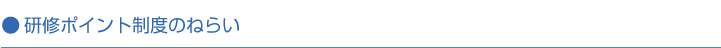
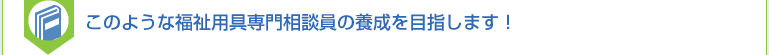
福祉用具専門相談員は、介護保険制度の担い手として、福祉用具の活用、住環境の整備という観点から、自立支援に資するケアマネジメントの実現を支える専門職です。そのような専門職として、以下のような福祉用具専門相談員の養成を目指します。
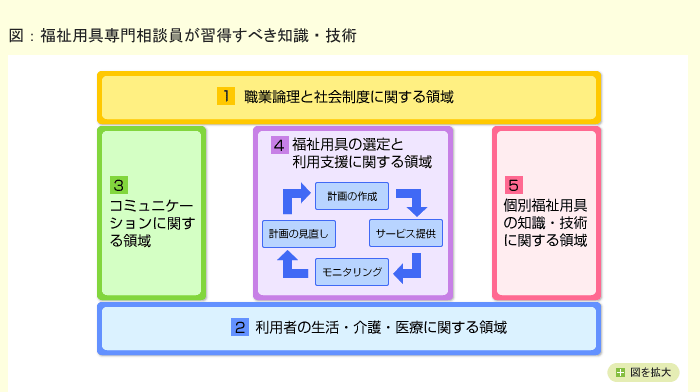
| ● | 利用者の生活の個別性を踏まえ、福祉用具の活用を提案している |
| ● | 福祉用具の支援プロセスに沿って、質の高いサービスを提供している |
| ● | 多様な福祉用具に精通し、自立支援に資する福祉用具の選定・適合を行っている |
| ● | チームケアの一員として、利用者の自立・尊厳を支えている |
| ● | 利用者やサービスの関係者と強い信頼関係を構築している |
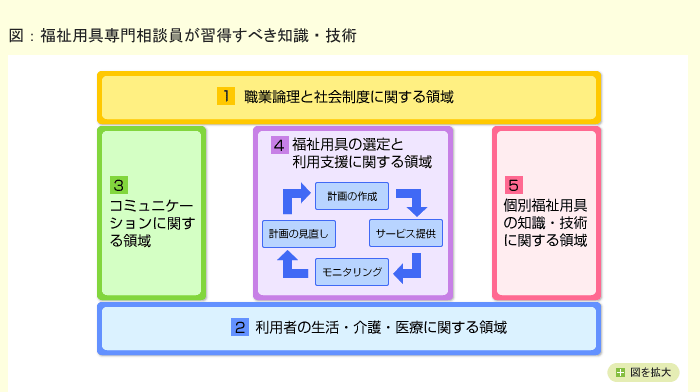
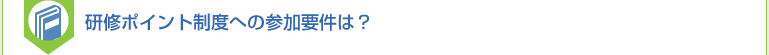
以下のすべての項目に該当する方が、制度にご参加いただけます。多くの方のご参加をお待ちしております!
| ● | 介護保険制度上で、福祉用具専門相談員の資格保持者として位置づけられている方 | ||||
|
|||||
| ● | 現在、福祉用具専門相談員として業務に従事している方 | ||||
| ● | 本制度のウェブサイト上で、氏名、会社名、研修ポイント実績等が公表されることに同意いただける方 |
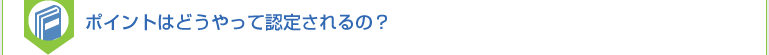
本制度で認証されている研修を受講し、証明書類とともに事務局に申請すると、審査のうえ、ウェブサイトにポイントが反映されます。

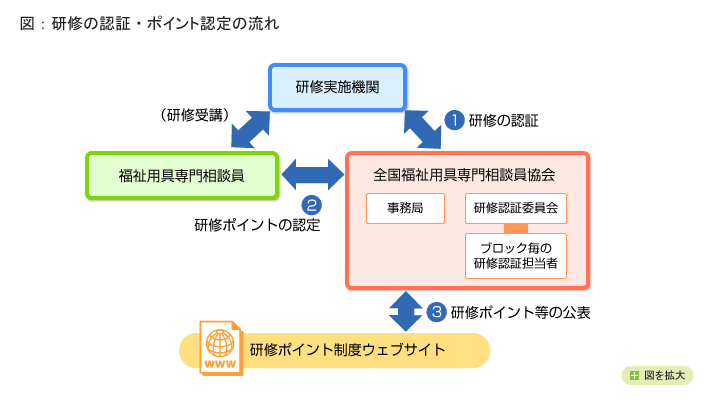

「研修認証委員会」で審査・認証された研修が、ポイント付与の対象となります。
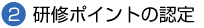
本制度に参加している福祉用具専門相談員は、①で認証された研修を受講したら、ポイントの申請を行うことができます。
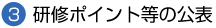
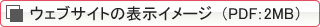
個人の取得ポイント等は、ウェブサイトで公表されます。
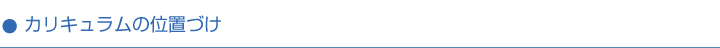 「研修認証委員会」で審査・認証された研修は、ポイント付与の対象となります。
「研修認証委員会」で審査・認証された研修は、ポイント付与の対象となります。
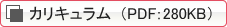
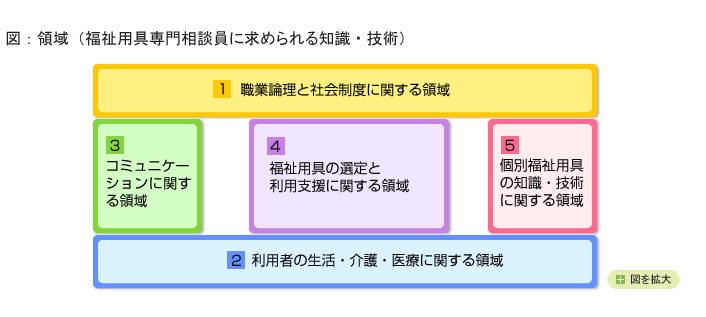

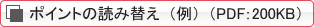

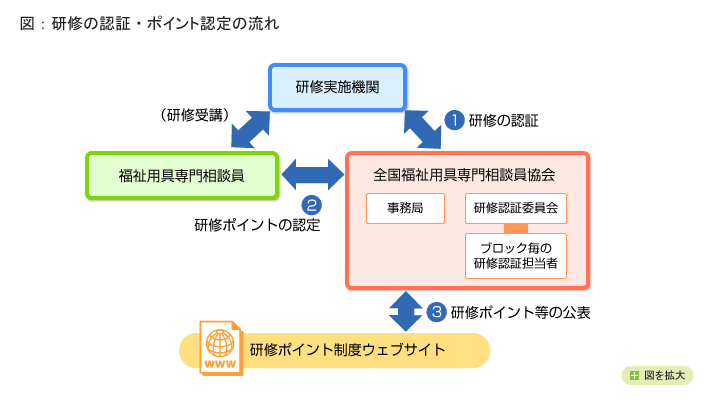

「研修認証委員会」で審査・認証された研修が、ポイント付与の対象となります。
| ● | 研修実施機関は、研修を審査・認証に諮るための申請をおこないます。 |
| ● | 研修認証委員会は、審査を実施し、研修を認証します |
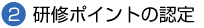
本制度に参加している福祉用具専門相談員は、①で認証された研修を受講したら、ポイントの申請を行うことができます。
| ● | 福祉用具専門相談員は、ウェブサイトからポイントの申請をおこないます。 |
| ● | 事務局は、申請内容を確認し、修了証の確認をもってポイントを認定します |
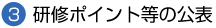
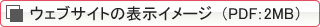
個人の取得ポイント等は、ウェブサイトで公表されます。
| ● | 事務局は、認証した研修、各相談員のポイント等を、本制度ウェブサイト上で公表します |
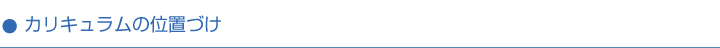 「研修認証委員会」で審査・認証された研修は、ポイント付与の対象となります。
「研修認証委員会」で審査・認証された研修は、ポイント付与の対象となります。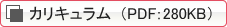
| ● | 福祉用具専門相談員に求められる知識・技術を、本制度における「カリキュラム」として表示しています。 | ||||
| ● | カリキュラムは、領域(下図参照)、科目、到達目標、研修に含むべき事項(例)、参考キーワードで構成しています。 | ||||
|
|||||
| ● | 福祉用具専門相談員には、本制度で認証された研修を組み合わせて、様々な科目を修得していくことを推奨しています。 |
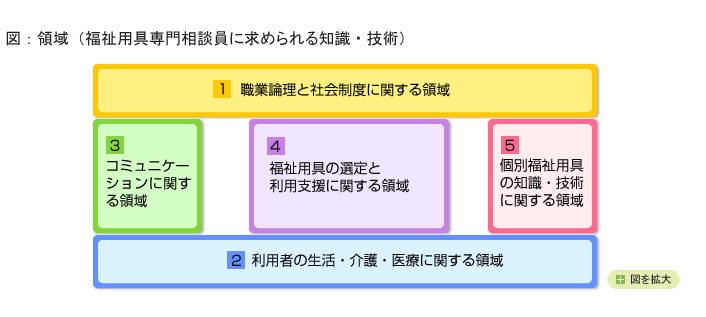

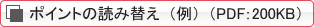
| ● | 対象となる研修の「科目」を、上記の「研修ポイント制度におけるカリキュラム」に沿って読み替えます。 |
| ● | ポイントは、各「科目」に対して付与します。 |
| ● | 原則として、60分に対し、1ポイントを付与します。(小数点第1位四捨五入) |